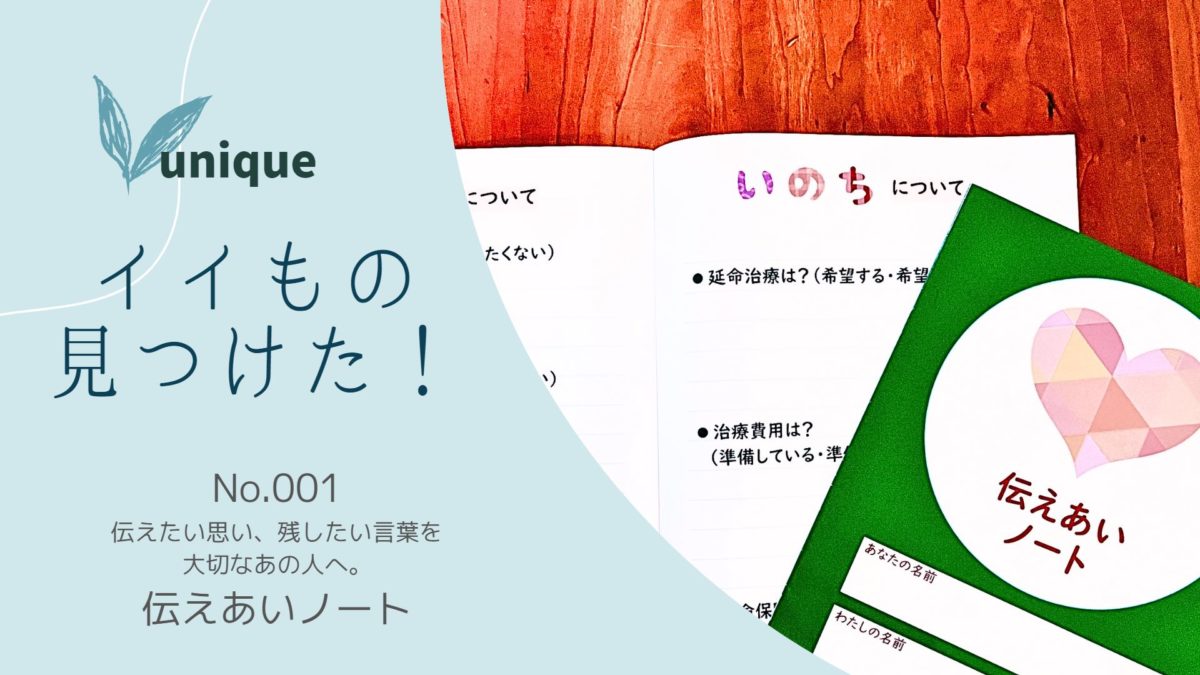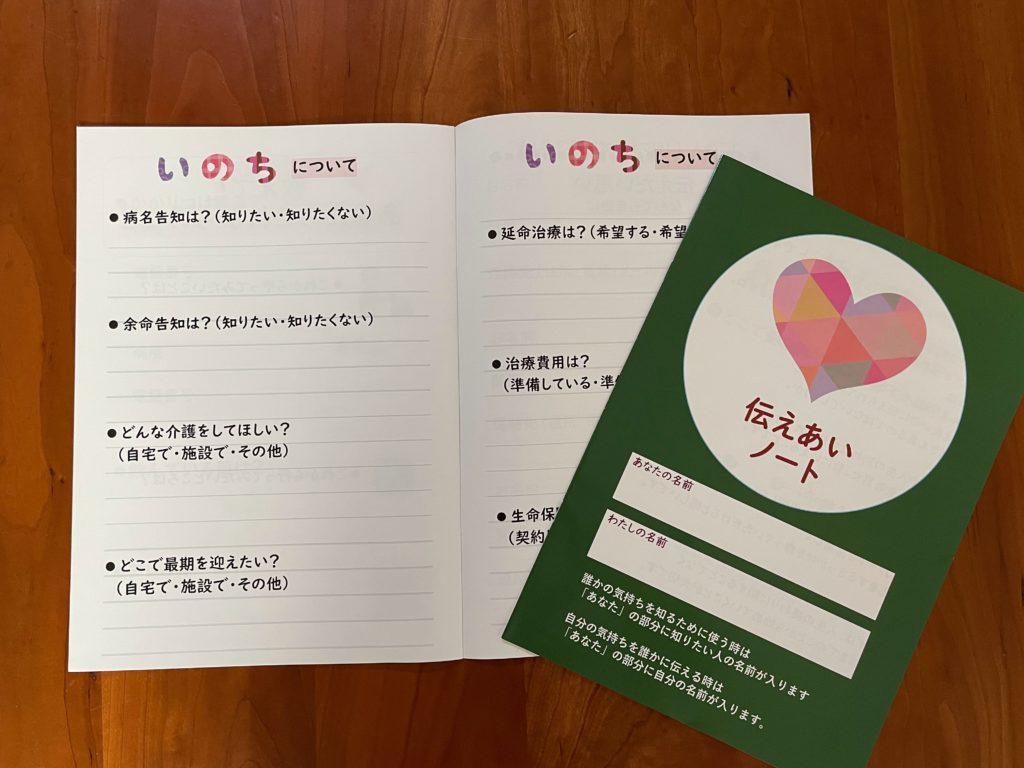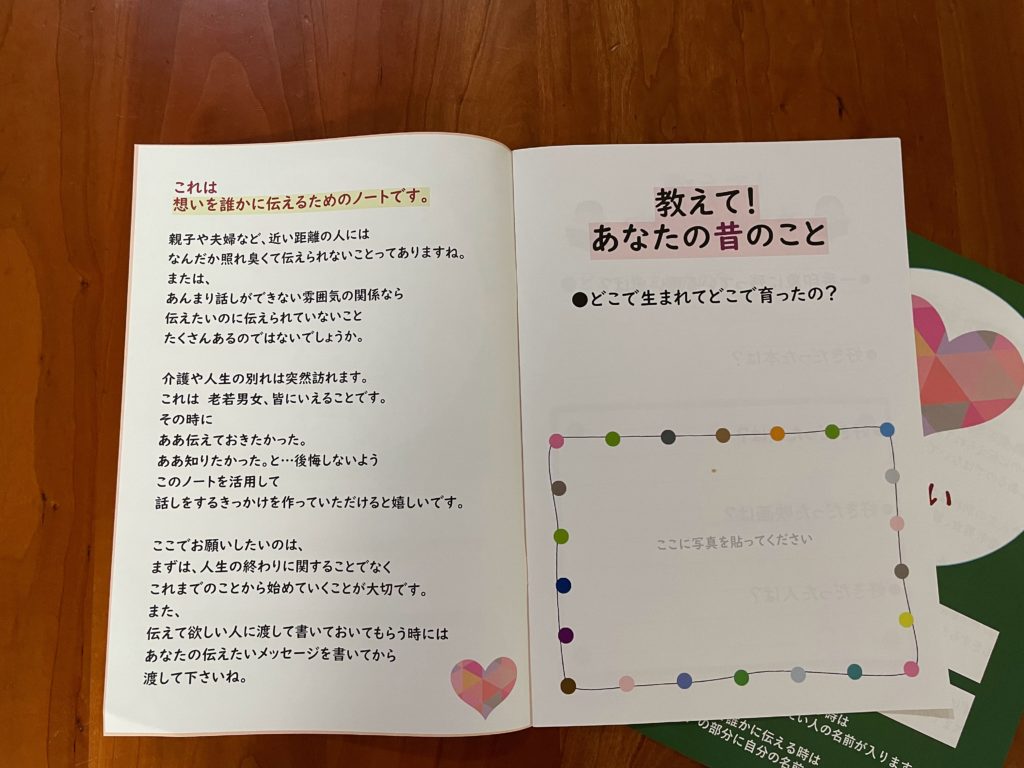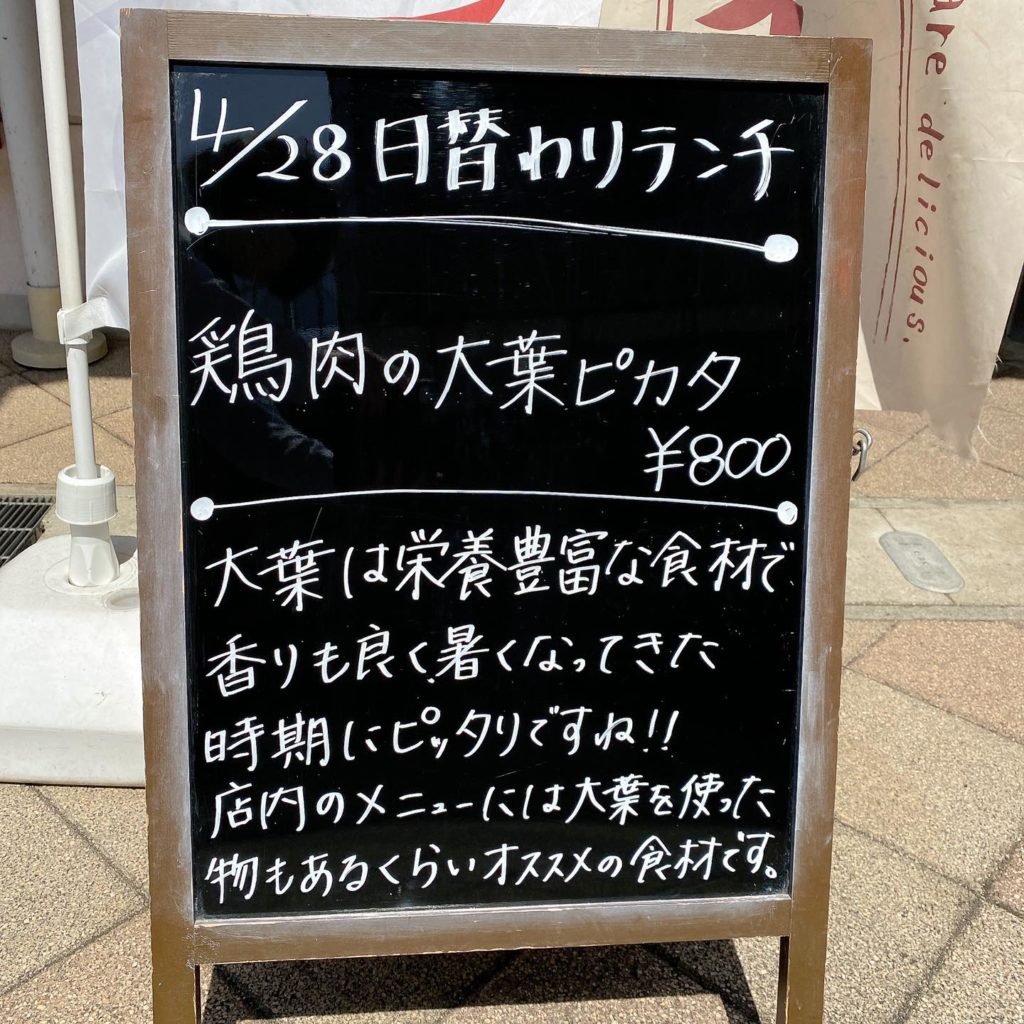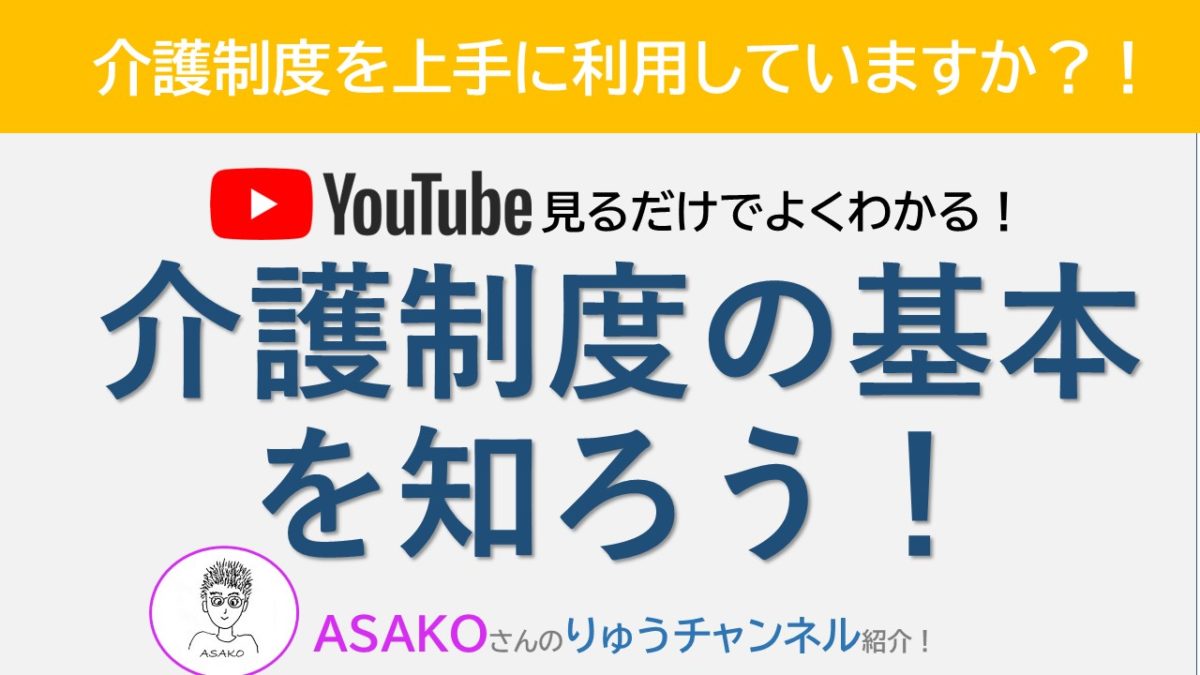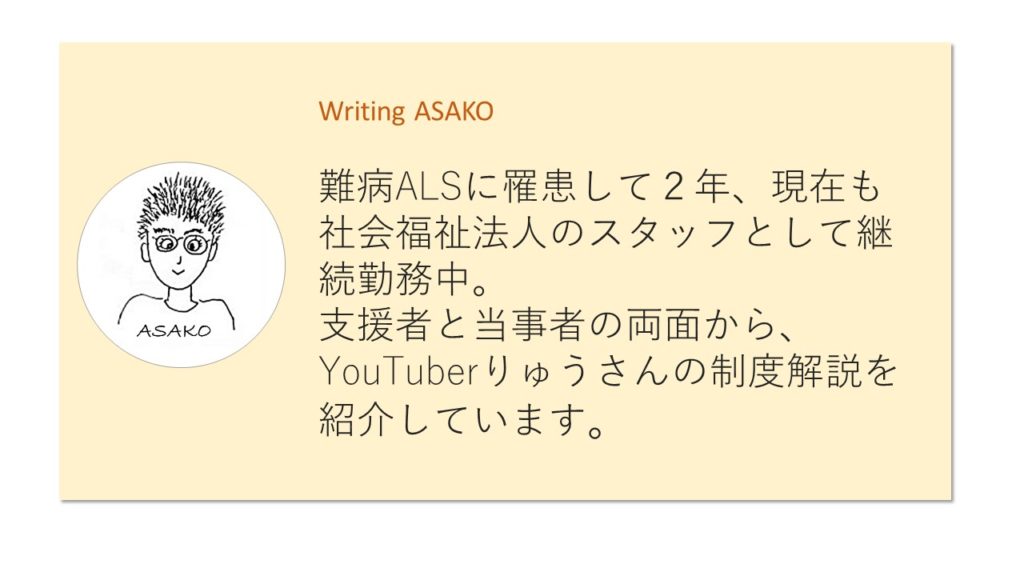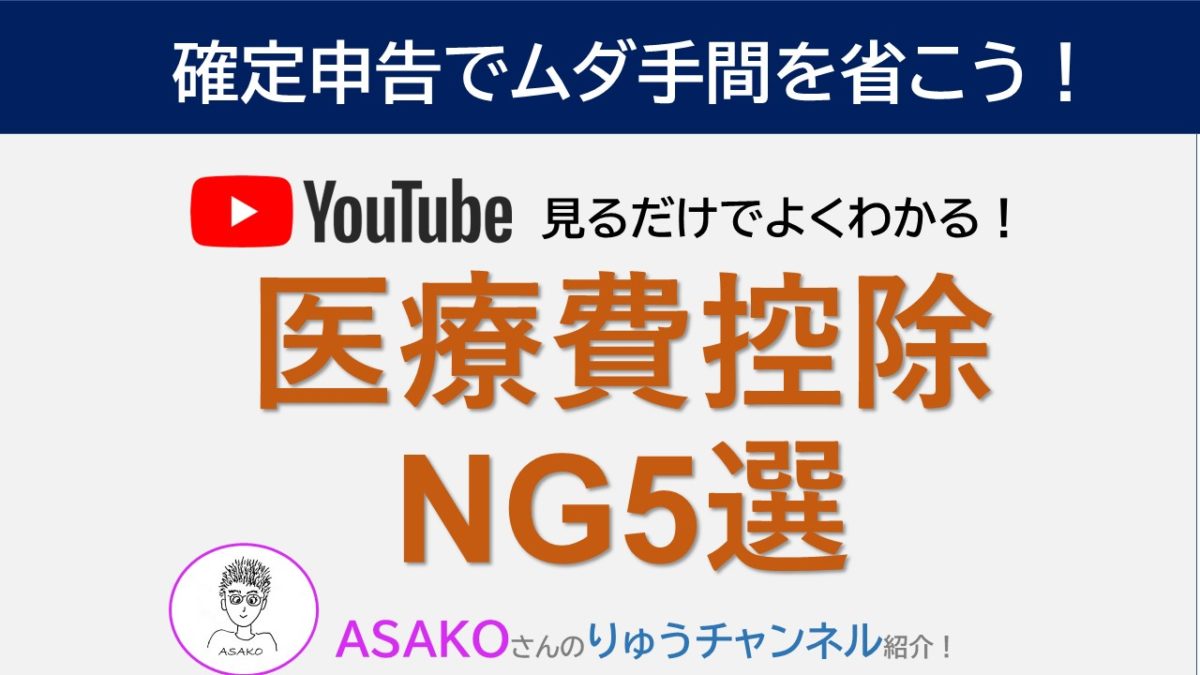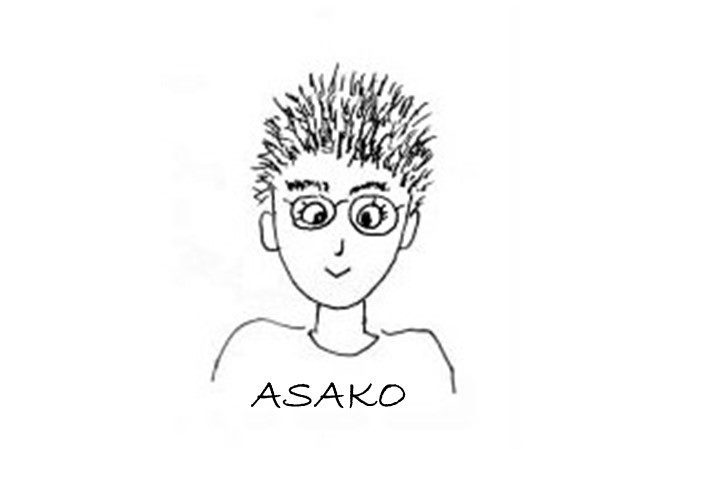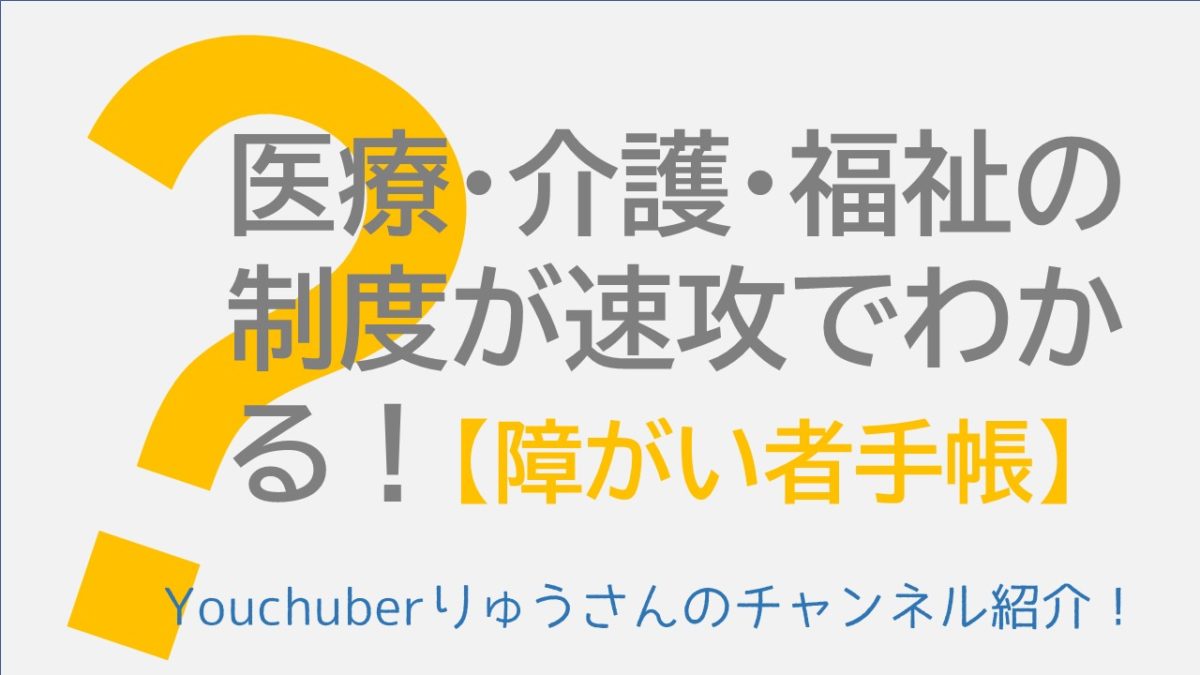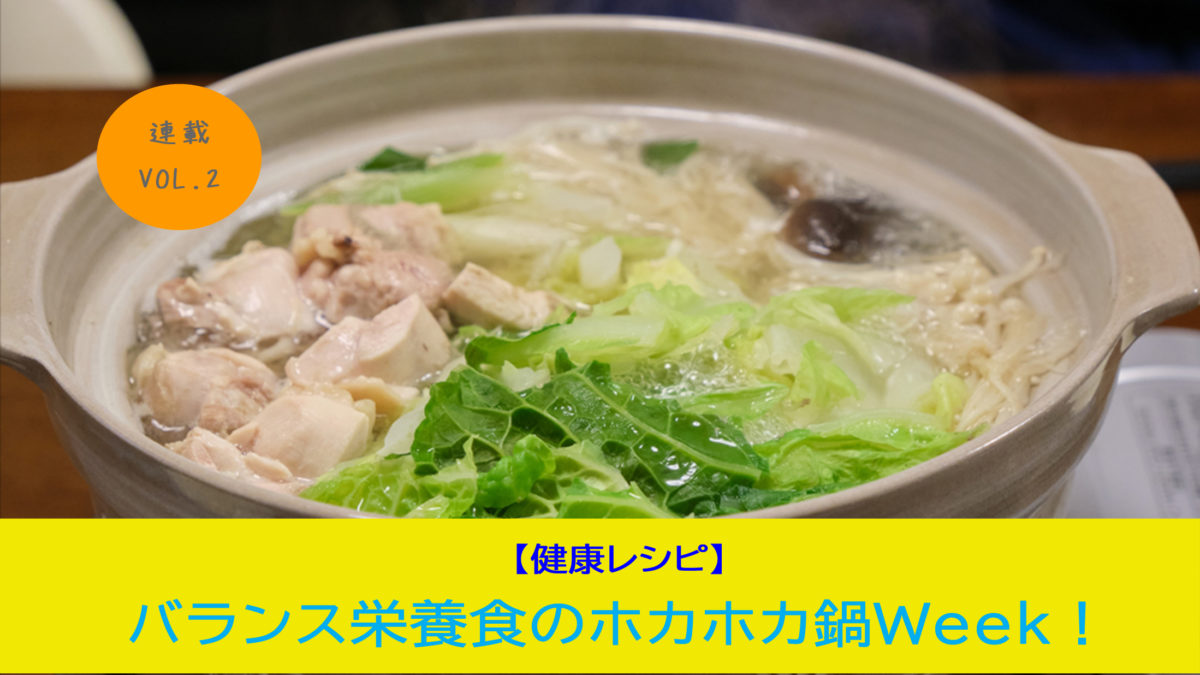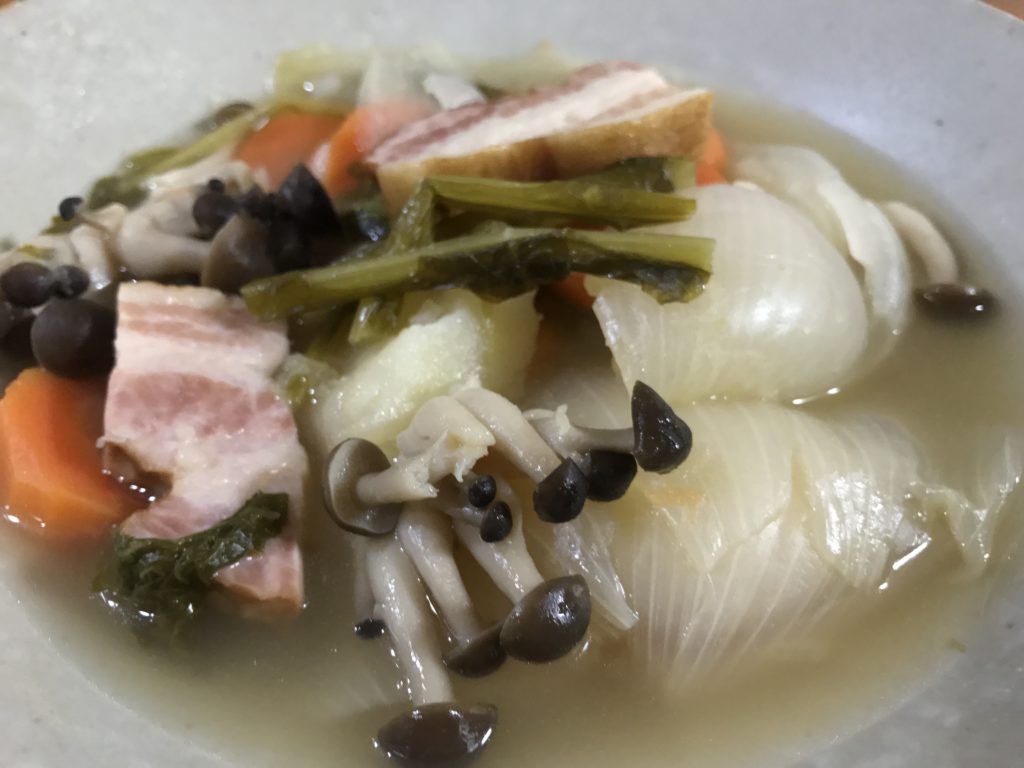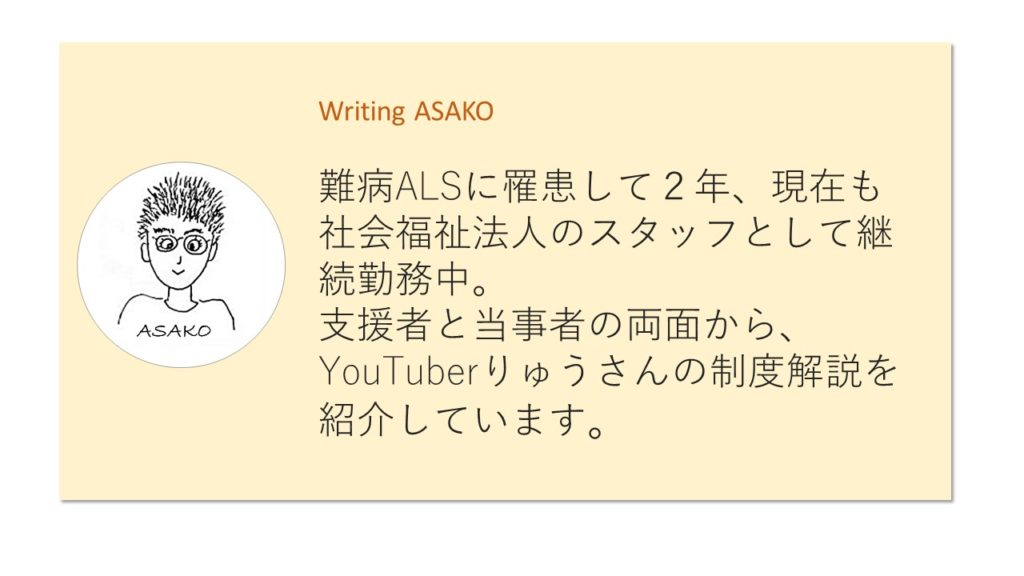
介護制度をざっくり解説!
80歳のおばあちゃんが脳梗塞で突然倒れて介護が必要になったら…、という一つの例にそって介護保険の制度を説明する動画です。
「対象は、原則65歳以上」、「1割の額の負担でサービスを利用できる」、「状態によって介護度が決まる」などの基本的な内容を、りゅうさん流にかみ砕いて分かりやすく伝えています。
「ケアマネさんってなにをする人?」
「サービスにはどんなものがあるの?」
そんなことも、ざっくりと分かります。
基本から少しそれますが、「40~64歳で、認知症、リウマチ、末期癌の方も介護保険を利用できる」という大事な内容に触れています。
65歳以上でなくとも、介護保険で定められた介護が必要になる病気であれば利用できるんですね。
特に、人口の2人に1人はかかる病気と言われる癌。
さまざまな治療法が出てきて、癌と共存する人が増えています。癌の末期という制限はあるものの、介護保険サービスが利用できるということも初めて知りました
ALS患者の場合、65歳未満でもサービスを受けることができます。診断時40歳をすぎていた私は、介護保険にずっと助けられています!
介護保険は65歳以上の人だけのものではありません。ざっくりと制度を知っておくのは、どんな年代の人にとっても安心材料になると思います。
医療と介護・39の職業!健康を支えるお仕事大集合!
自分がどのような職種の方々のお世話になっているか。または、直接お世話になっていなくても、支えてくれている方々のことを知ることは、難病や障害の当事者として生きていくときの力になると思って、この動画をご紹介します。
「医療と介護のお仕事」を皆さん、どれだけ知っていますか?
私は10も思い浮かびませんでした。
実際に、私のサポートに関わってくれている方々を職業別にみると、現在はそのくらいの数なのです。
デイサービスでは介護福祉士やホームヘルパー、訪問では作業療法士や言語聴覚士、マッサージ師、病院では医師や看護師です。
でも、世の中にはその何倍もの職種が存在し、患者さんや介護保険サービスの利用者を支えていることを動画を観て知ることができました。
自分が今の生活を継続できるのは、医療や介護という職域だけでなく、社会全体に支えられているからなんですね。
例えば、病院からの依頼で患者さんの画像データを管理する医療系IT企業や病院の経営を守る医療経営コンサルタント。
一見、自分に関係のない仕事のようですが、どれかが欠けてしまうと私たちの療養生活に影響が出て、現状維持が難しくなるのだと思います。
そんなふうに、視野を広く持つことの大切さにも気づかせてくれた動画です。