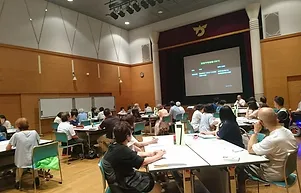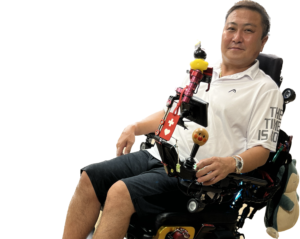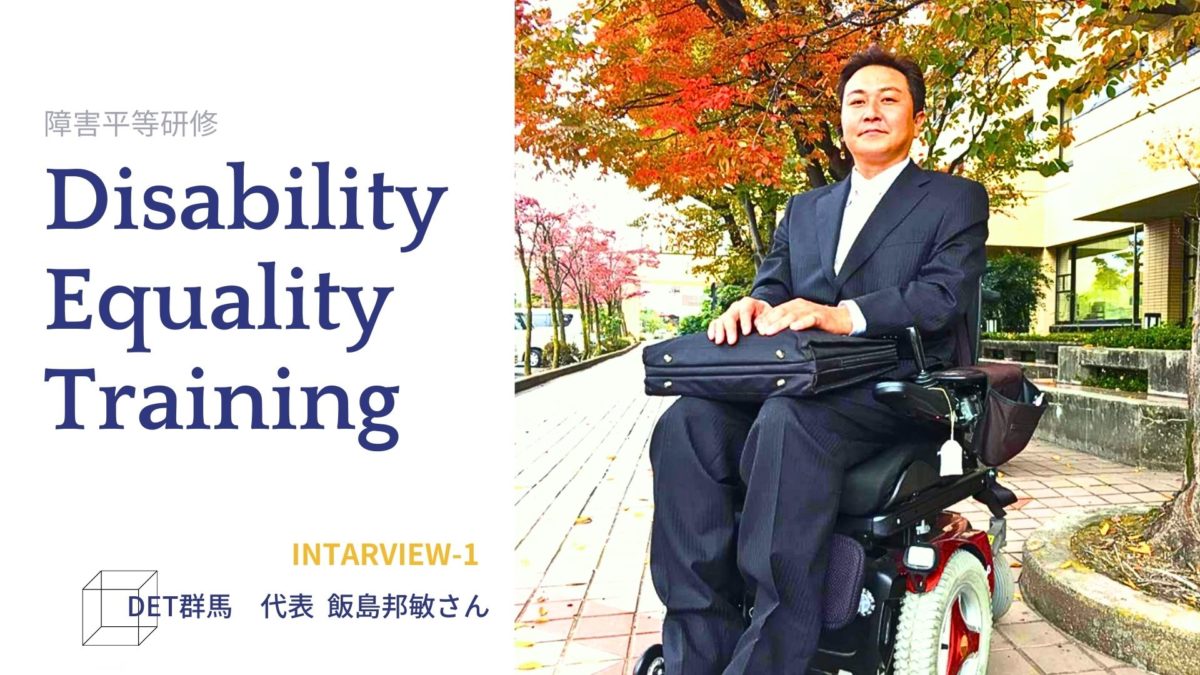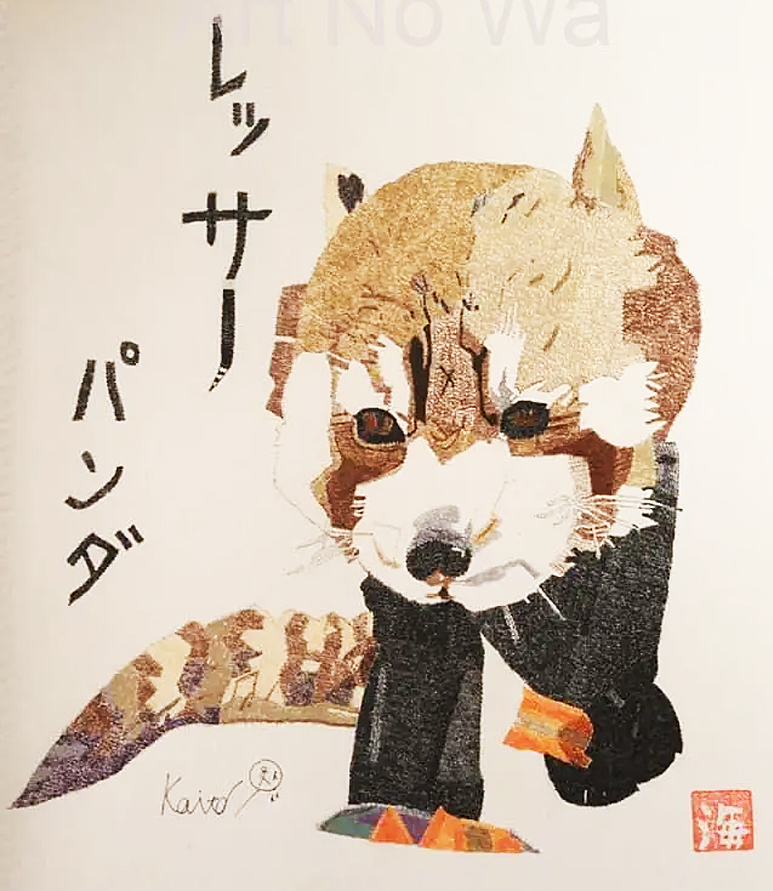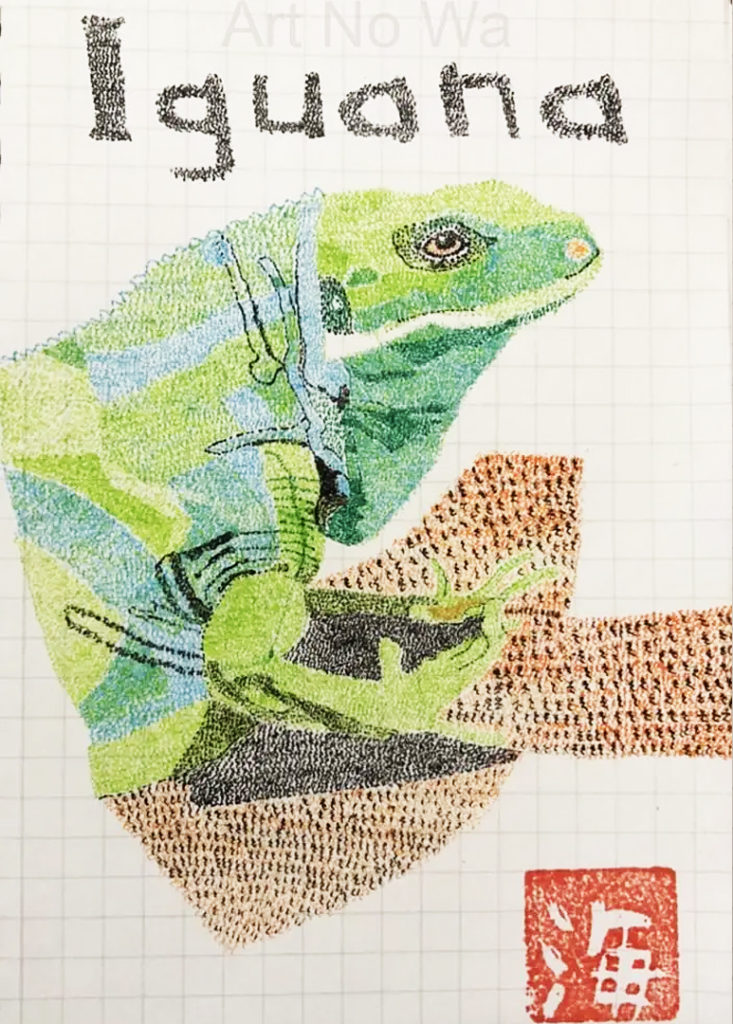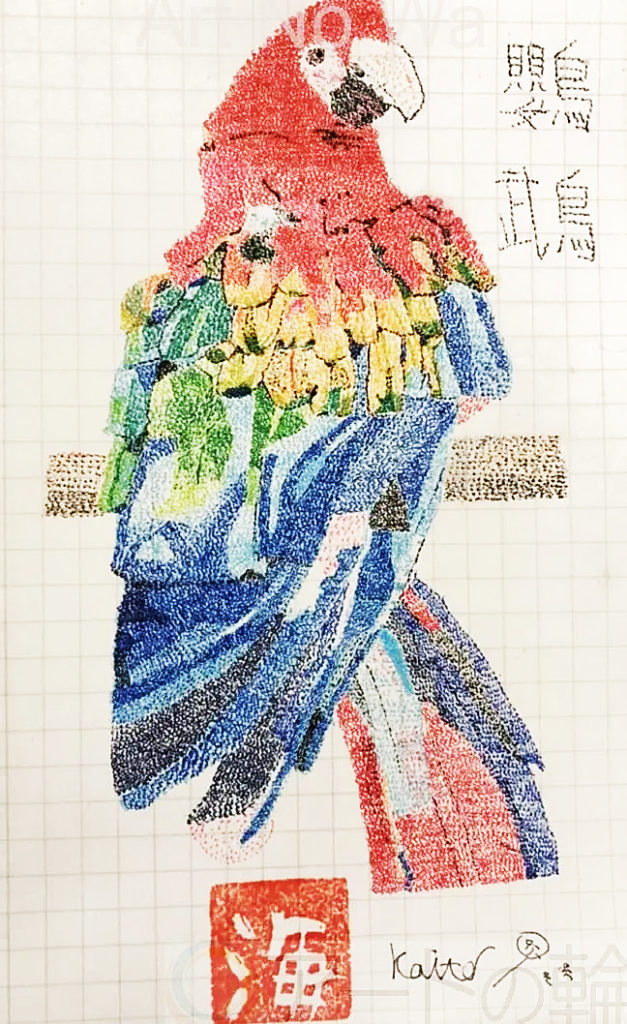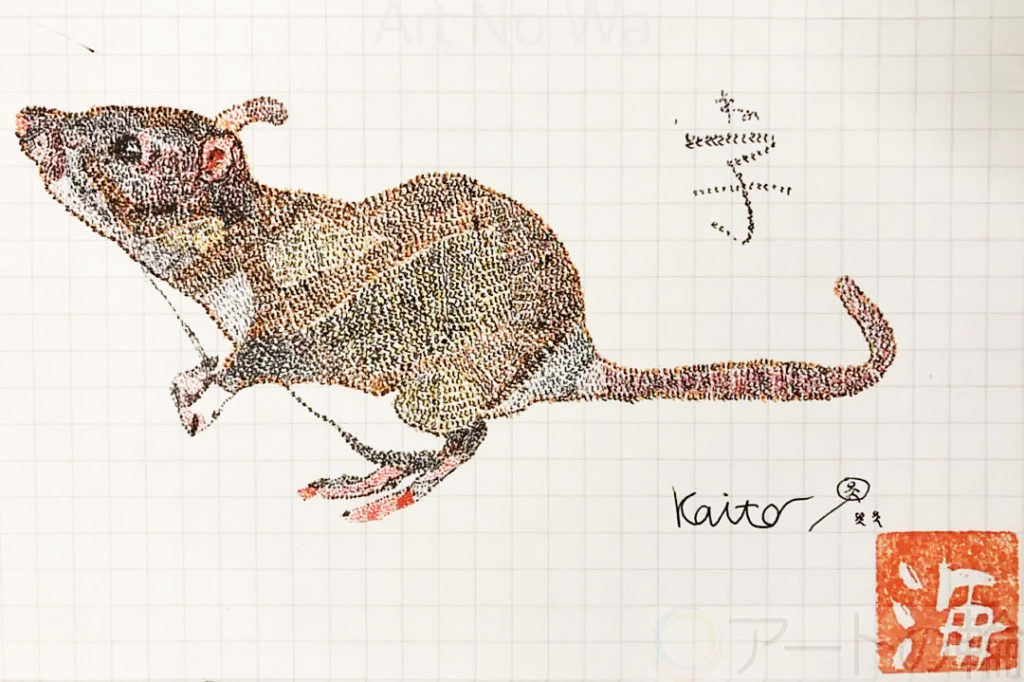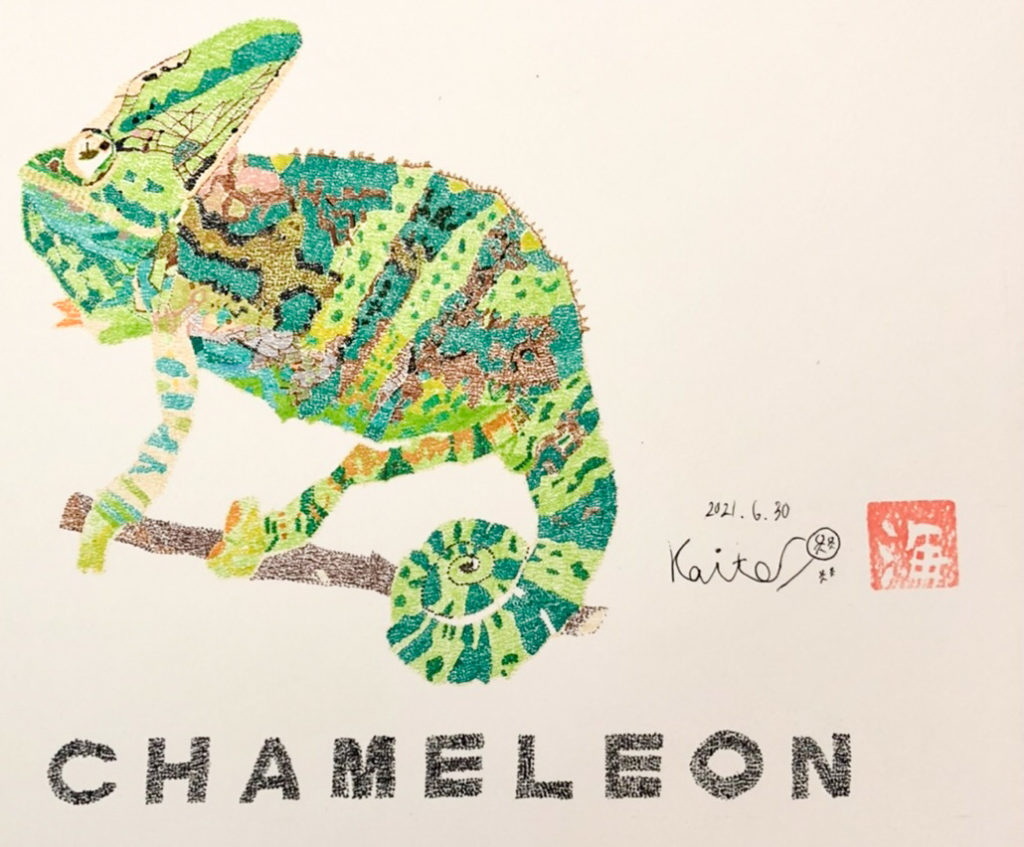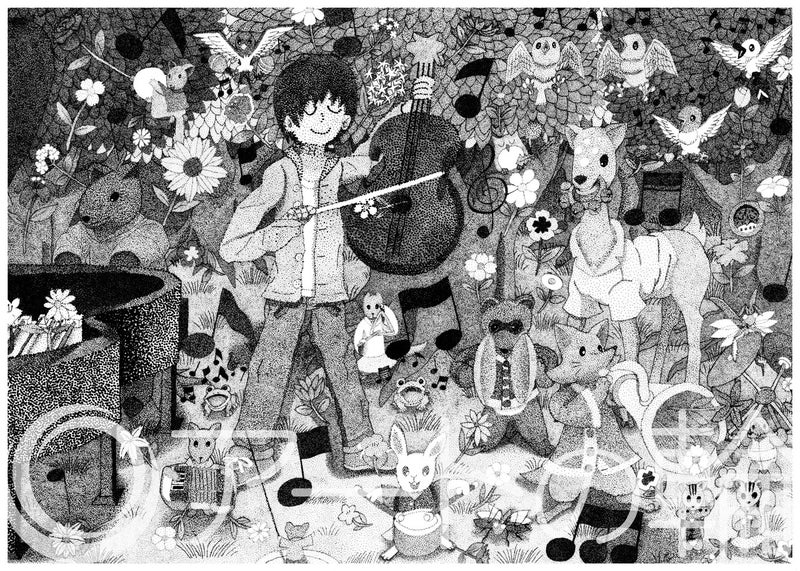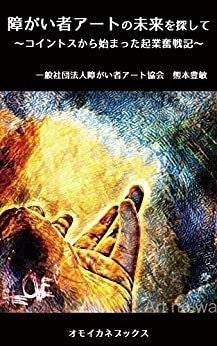現在クラウドファンディングに挑戦し、食による心身のケアを主とした活動を精力的に行っている井上美穂さん。
枠にはまらないその発想力と行動力は、いつでも人をわくわくさせたり、やさしい気持ちにさせてくれます。
3年ほど前、美穂さんとは一冊の冊子が縁で知り合うことができました。その冊子は、栄養バランスを考えたコンビニでのお弁当、総菜の選び方をアドバイスした内容で、実際に販売されている品々が写真で紹介されていて、とても分かりやすくて実用的に仕上がっていました。これまでにない新しい視点でこんなに丁寧に食する人のことを考えて作ったことが伺える一冊。きっとかなりのエネルギーを要したことでしょう。
これを美穂さんがほとんど一人で作りあげたという話をきいて、彼女の思いの強さに心が動かされたことを今も覚えています。
訪問栄養指導が活動の出発点に。

手作りではなくコンビニ食での栄養バランスをテーマにしたのは、
「その冊子は栄養指導で訪問する患者さんや介護者の方に配りました。コンビニやスーパーでお弁当や総菜を買っている一人暮らしの高齢者がすごく多くて、そうしたお年寄りの偏った食や孤食の現状をどうにかして変えるきっかけを作れたらと思ったんです」
冊子は「こんなのが欲しかった!」と、患者さんだけでなく介護職の方にもすこぶる好評だったようです。美穂さんはそんな喜びの声を聞くたびに、食生活の問題をいかに多くの人が抱えているかを身近に感じて、自分の目指す方向が見えてきたと言います。
キッチンカーで新しい食の提案を始動!

美穂さんは現在、会社勤めを辞めて、食と栄養をテーマに様々な活動を仕事として行っています。
その一つがキッチンカーによるバランスのよい食の提供です。
「キッチンカーでの活動は、訪問栄養指導の際に患者さんが言った『何を食べたらいいかわからなくなった』という言葉がきっかけで始めました。毎日、一人でぼそぼそとコンビニ弁当を食べていると食に対する興味も楽しみもなくなってしまうんです。何を食べてもおいしいと思えない。食べたいという気持ちさえどんどんなくなっていく。ゆっくりと話す時間のない中で栄養指導をしていても、何も変えることのできない自分に無力さを感じました」
時間に追われながら生活する人、いつも一人で食事をする人が増えている現代では、日々の食事を大切に思い、楽しむ気持ちはどんどん薄くなっていっているのかもしれません。
「食事を楽しむことは、心と体の栄養に繋がっていくはず。キッチンカーを通じて温かい食事を届けるだけでなく、栄養面での相談にも対応しています。誰でも気軽に心配なこと、困っていることを話せる“おしゃべり相手”になれたらいいな、とそんな思いで活動を始めたんです」
クラウドファンディングに挑戦!

そんな美穂さんは、今クラウドファンディングに挑戦しています。
美穂さんの目標は3つ。
1.誰でも管理栄養士に相談ができる移動型の【食の相談室】を作る!
2.キッチンカーを通じて外出のきっかけを作り、閉じこもりを防ぐ!
3.食事を通して、何をどれくらい食べたらよいか感じてもらいたい!
「今回のプロジェクトの目的は、このキッチンカーで、地域の方に温かいお食事を届けることです。現在はレンタルの車両を使わせていただきながら週に1度、オフィス街で販売し、少しずつですが地域のイベントにも参加させていただけるようになりました。
そんな地道な活動を続けていくと、地域の介護や医療のイベント、高齢者施設、団地やスポーツイベントにも声をかけていただくようになり、今年はもっと地域に目指したキッチンカーに成長するためにクラウドファンディングに挑戦させていただきました」
「“お節介”なワタシに気軽に話しかけてください!」

管理栄養士に相談…と言われると、何から聞いていいのか、どんなことを教えてもらったらいいのか分からなくなって、質問が出てこない。そんな人、きっと多いと思います。〇〇の専門家という人を目の前にすると、ついつい身構えてしまう。
美穂さんは、そうした壁を取り払い、地域の中で一人でも多くの人と話をして、食事について考える機会を作ってもらうことが自分のミッションと言います。さらに必要な人には介護や医療につなぎ、地域のネットワークの繋ぎめを担うことも自分にとって大切な役割りと思っているそうです。
「私は、食生活に問題がある方に『食べてはいけない』と伝えるのではなく、どうすれば食べられるのかを一緒に考えていきたいと思っています。
人はみんなそれぞれ。これまで続けてきた食事の仕方があるので、それを否定するのではなく、受け入れた上でどうすれば少しでも長く自宅で過ごせるかを考え伝えていきたい。受け入れてもらうには、自分もその人の生き方を知って、受け入れることが大切なんですよね。
私のことを“お節介な人”って思う人、きっといますよね。
そう思ってくれるのはうれしいことで、私にとっては褒め言葉なんです。
必要な人へ必要な食事を届けたい。管理栄養士になった私の使命として、食の大切さをこれからも“お節介”しながら”伝えていきたいと思っています!」
クラウドファンディングは3月30日まで。
この記事を読んで、興味を持った方、自分の食事について考える機会になった方、どうぞ美穂さんのクラウドファンディングサイトを訪れてみてください。
★クラウドファンディングサイト
https://for-good.net/project/1000514

管理栄養士:井上美穂
急性期病院での栄養管理や給食管理を経て、在宅専門の薬局に就職し、訪問栄養指導業務を行う。
その後、個人事業主となり、キッチンカーでの食の提供を行いながら栄養指導を行う活動を始める。地域の誰もが気軽に会いに来れる管理栄養士を目指して、必要な人に必要な食事を届けたいという思いで活動中。
★食の相談室おむすび(キッチンカー)
・豊洲センタービル/水曜日・11:00~14:00
・THE TOYOSU TOWER/水曜日・16:00~20:00
※4/3以降はOtemachiOne/水曜日・11:00~14:00に変更
★ふれあい歯科ごとう(訪問栄養指導)
木・金曜日(時間は相談に応じて)
東京都新宿区北新宿4-11-13せらび新宿1階
TEL 03-5338-8817
HP:https://fureaishikagoto.com/
★Sunny days Cafe(介護相談もできるカフェ)
月・土曜日(土曜は第2・4のみ)・11:00~17:00※ランチは11:30~14:00まで
東京都新宿区上落合1-9-11 レミコ学院ビル1階
TEL:03-5358-9920
HP:https://sunnydayscafe.hp.peraichi.com/